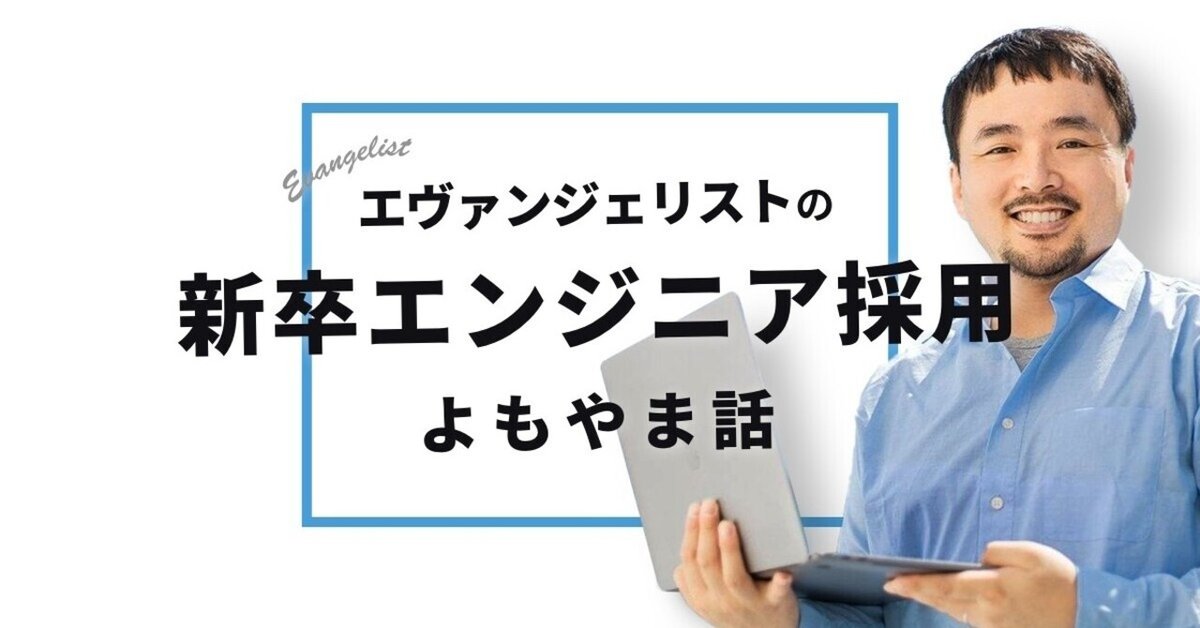
エンジニア新卒採用に向けた社内体制構築方法
サポーターズ エバンジェリストの久松です。他に合同会社エンジニアリングマネージメントにて社長兼「流しのEM」として複数企業で組織づくりなどを担当しています。本noteでは、新卒エンジニア採用に関する「よもやま話」を月1ペースで発信して参ります。(第一回は以下)
今回は新卒ITエンジニア採用体制の構築方法についてです。
なぜ人事だけの採用体制では不十分なのか?
昨今、新卒に限らずエンジニアの採用難に伴い、採用の場にエンジニア正社員がアサインされるケースがあります。一部のエンジニアからは「採用担当が居るのだから採用担当だけで完結するべき」と言われることもあります。
しかし、現在は会社選びにあたって「会社の雰囲気」が重要視されます。そのため、他社はというと接触の段階からCTOやVPoEが登場し、実際の働き方などを想起してもらうためにエンジニア正社員も面談に同席したり、採用イベントに参加して貰ったりしています。他社は現役エンジニアが詳細な開発や在籍しての経験を話すのに対し、非エンジニアの人事だけが出て行っても分が悪いのは明白です。
実際の例としてエンジニアが新卒採用の場に出てこなくなった企業がありますが、採用できるのはポテンシャル採用や第二新卒採用のみとなっているようです。なぜエンジニア新卒を採用するのかにも寄りますが、採用要件が高いのであれば人事採用担当だけでは困難だと思って良いでしょう。
社内のタレントピックアップ
経験上、下記の要素に当てはまる人物に働きかける必要があります。
社内で活躍している
自社の理想となる採用人物に近い
人と話すことが苦ではなく、むしろ好きである
後輩の育成などが好きである
エンゲージメントが高く、離職の予定がない
特に一番最後のポイントは重要です。エンゲージメントが下がっていると、学生からの「この会社のどこが良いですか?」などの質問がとどめとなり、退職してしまうこともあります。
理想としては年齢が近いとより働くイメージが湧くため有効です。もし数年以内に新卒採用を実施済みであれば、彼らをアサインすることである程度候補者側の気持ちも分かるので優位です。新卒が居ない場合は近しい年齢の中途採用者をお勧めしています。
事前準備としての会社紹介資料
新卒採用において会社紹介をする場は多く存在します。各種採用イベントで企業プレゼンをするだけでなく、カジュアル面談をする際にも利用します。
この際、採用対象に近しい人を3名ほどピックアップし、下記の要素を会社紹介資料に書くと良いでしょう。
出身大学や大学の専攻
入社理由
入社時から現在に至るまでの略歴
現在の業務内容
にこやかな写真
このように自社に入社することによって候補者が働くイメージが湧き、活躍できるイメージを持つことが重要です。
タレントを利用した新卒採用
次に具体的にピックアップしたタレント達にどういう観点で採用に参加して貰うかについてお話ししていきます。
1on1イベント、採用イベントへの参加や登壇
ITエンジニア新卒採用では1on1イベントと言われるものがあります。ブースを構えている学生達のところに企業が1-3名で訪問し、これまで取り組んできた活動を聞きつつ、企業説明を交えながらスカウトしていくスタイルのものです。
また、サポーターズで言うところの学生エンジニアのアウトプットを展示する技育展などといったものや、ハッカソンを行うケースもあります。
これらいずれのイベントもアウトプットに対する技術的なコメントを学生にすることによって「企業に入ってからの成長可能性」が感じられるきっかけになるため、人事だけで乗り込んでいっても技術的なフィードバックができずに厳しい側面があります。
何かしら技術的にポジティブにコメントできたり、自身が新卒だった時の経験を踏まえてアドバイスできる人をアサインしましょう。
面談
中途同様に新卒であってもカジュアル面談を実施することが一般的です。カジュアル面談では企業説明、事業説明なども行われますが、普段の開発の様子や、何故この会社を選んだのかといった質問を通し、候補者自身が働くイメージをどれだけ持つことができるかがポイントになります。
この際、想定される質問としては下記のようなものがありますので、事前に社内で準備しておくことをお勧めします。
研修体制の有無、内容、期間
社内勉強会など互いに研鑽する風潮
採用している技術スタック
開発チーム体制
今後取り組む予定の課題
施策についてのエンジニアの関わり方(提案はできるのか、言われたものを作る社内受託なのか)
エンジニアの1日の過ごし方
評価制度
キャリアパスイメージ(1年後にどうなり、2年後、3年後にどうなれるのか)
新規事業の予定とエンジニアとして関われる可能性の有無
チームやプロジェクト異動の有無
平均残業時間
リモートワークの有無、もしくは住んでいるところや家賃
研修体制については、2020年頃までであれば手厚い研修を求める候補者はSIerに行き、そうでない自走できる学生は自社サービスに行く傾向がありました。しかし現在は有名メガベンチャーを志望して内定が出る学生であっても、(手取り足取り程ではないですが)何かしらのバックアップ体制がある状態を望む傾向にあります。コロナ禍による学生生活のオンライン化に加え、政情不安による漠然とした不安が背景としてあると考えられます。
また、給与の上がり幅については注意が必要です。以前「2年で○○万円貰えるようになれる」と断言してしまい、入社後に実現されずに蜂起が起きた事例を耳にしたことがあります。給与などはメンバーシップ型採用で年功序列を採用していない限りは「個人の成果次第」でしょう。
また、平均残業時間も概ね労務部門が把握しているものであり、1エンジニアでは回答に困るところでしょう。
このような事態に備え、人事もしっかりと介入した上で「FAQに対する公式回答」を準備しておくことをお勧めしています。
内定承諾後のメンター
選考プロセスを経て内定を出したら終わりではないのがここ数年の傾向です。職種問わず耳にしていることですが、内定を持っている学生というのは当該企業の選考を潜り抜けたという価値があるといえます。そのため2018年頃から内定承諾者を狙っての声かけをする企業が企業サイズを問わず確認されています。
また、大学院進学と悩むケースもあります。大学院入試が終わった後であっても、卒業を遅らせたり半年ブランクを作った後に半年後の入試に挑むケースもあります。
企業によっては内定者10名に対し1名が辞退したり、5名に対し1名が辞退したりします。このような内定承諾後辞退に対応するために定期的にコミュニケーションを取る必要があります。
人事採用担当が窓口に立つケースもありますが、入社後のメンターを内定承諾後に先立ってアサインしてしまうというのも効果的です。少なくとも1ヶ月に1回は面談をし、人事や開発部内で状況共有することをお勧めしています。
採用協力者に評価でのフィードバックを
エンジニアには採用協力者として実務(プログラミング)の時間を削って面談対応してもらうことになります。また、土日に採用イベントがある場合は代休の調整などをしてもらわなければなりません。これらがかなり負担となるためボランティアとして強要するとうまく行かないどころか、疲弊して採用協力者本人が退職するケースもあります。
あくまでも業務の一環であると位置づけ、人事部と開発部で握っておくことをお勧めしています。対象者がエンジニアリングマネージャーであれば採用人数を目標に据えるのも良いでしょう。それ以外のメンバーであれば採用活動に参加したことを行動評価のいずれかの項目で評価できるようにすることをお勧めします。
人事部門だけで採用できる状態は無くなっているのが現状です。一方でボランティアのような形で協力は本業である開発に影響があるため望ましくありません。是非前向きにエンジニアに採用に協力して貰えるような体制を作るようにしていきましょう。
・・・



